原作、映画、両方みたのでその感想を。
まずは、原作小説から。
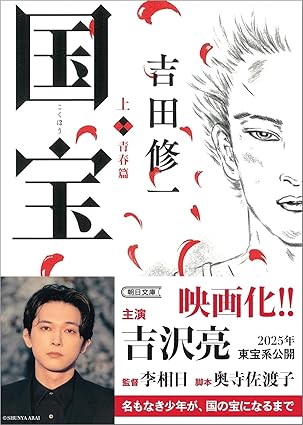 |
| 国宝上青春篇 (朝日文庫) 著者:吉田修一 |
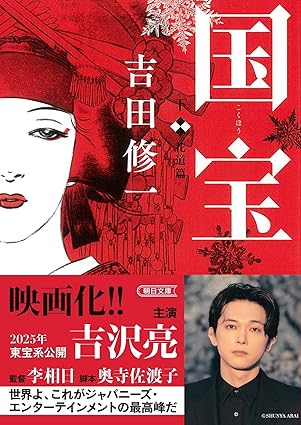 |
| 国宝下花道篇 (朝日文庫) 著者:吉田修一 |
あらすじ
1964年元旦、侠客たちの抗争の渦中で、この国の宝となる役者は生まれた。
男の名は、立花喜久雄。任侠の家に生まれながらも、
その美貌を見初められ、上方歌舞伎の大名跡の一門へ。
極道と梨園、生い立ちも才能も違う俊介と出会い、若き二人は芸の道に青春を捧げていく。出典:『国宝 (上) 青春篇』 裏表紙より
上下巻あわせて、700ページ越えの超大作!
突然だけれど、本文中に印象的なセリフがあるので引用します。
主人公、喜久雄の才能を見出す場面。
男が女を真似るのではなく、男がいったん女に化けて、
その女をも脱ぎ去ったあとに残る「女形」というものを、
本能的に掴めているのでございます。出典:『国宝 (上) 青春篇』p143より
これが、役者の真髄、それとも心髄か。
これをふまえてのラスト。
最後の展開を読んだ時、3度読みした。
それほどの喪失感だった。
はたからみたら花道を飾ったともとれるかもしれないが、
私は「あぁ、抜けたんだな。」と思った。
抜けたのは、人としての何かとも思うし。
とにかく、何か抜けた気がする。
歌舞伎は、てんで詳しくない、ほぼ知らないんですが、
ちゃんと演目の解説も入るので、理解不能にはならず、
最後までついていくことができました。
ついていけたから、あのラストは余韻がずっと残ります。
では『国宝』の内容ですが、
世襲に重きを置かれる歌舞伎の世界で、
芸の腕だけで、戦い抜いていく主人公喜久雄の話。
と、書くと単純にみえますけれど、
本編は波乱万丈なんて言葉が生温いくらい
不幸が矢継ぎ早に喜久雄に降りかかります。
親の死、友との別れ、先輩からのイビリ、
世間からの非難、恋人の失踪、などなど。
これでもかっていうくらいどん底にたたき落されていく喜久雄。
彼は底辺からはい上がるために、誰かをダマしたりすることも。
重苦しい話は多いけれど、本書の語り口は漫談のようで
ピリピリした雰囲気を和らげてくれているので読みやすい。
ひとつ気になったのは元は週刊連載だったらしいので、
あとから「実は、こうでした」展開が多いところ。
そんなことを思っていたら、
それを解消してくれたのが映画版です。
国宝
出典:映画『国宝』公式サイトより
公開:2025年6月(日本公開)
製作国:日本
監督:李相日
あらすじ
後に国の宝となる男は、任侠の一門に生まれた。
この世ならざる美しい顔をもつ喜久雄は、抗争によって父を亡くした後、
上方歌舞伎の名門の当主・花井半二郎に引き取られ、歌舞伎の世界へ飛び込む。
そこで、半二郎の実の息子として、生まれながらに将来を約束された御曹司・俊介と出会う。
正反対の血筋を受け継ぎ、生い立ちも才能も異なる二人。
ライバルとして互いに高め合い、芸に青春をささげていくのだが、多くの出会いと別れが、運命の歯車を大きく狂わせてゆく…。誰も見たことのない禁断の「歌舞伎」の世界。
血筋と才能、歓喜と絶望、信頼と裏切り。
もがき苦しむ壮絶な人生の先にある“感涙”と“熱狂”。何のために芸の世界にしがみつき、激動の時代を生きながら、世界でただ一人の存在“国宝”へと駆けあがるのか?
圧巻のクライマックスが、観る者全ての魂を震わせる―― 。出典:映画『国宝』公式サイトより
原作の前後する時間軸は順番どおりに整理されてます。
やっぱり、映画化で一番大きいのは「音」と「舞」ですね。
文章よりも、さらに妖しさがマシマシです。
役者の話なので、話し方の演技、雰囲気を作る囃子。
それは、原作と合わせて映画を見ると、より伝わってくるというか。
特に、女形の色気。
吉沢亮の色気は言わずもがなだけど、
序盤の黒川想矢の舞も、ドキッとした。
冷めた孤独感みたいなものに引き込まれる。
ちょっと、ビックリしたのは、
歌舞伎にヴァイオリンをあわせるという思い切った演出!
意外にも喜久雄の孤高な感じにあるな~。と。
原作ではオペラに合わせて歌舞伎を演じたので、それを意識してのことかな。
ただ、やっぱり映画なので、展開をだいぶ省略してます。
その影響か、印象が変わった部分がひとつあります。
それは…悪い人がいなくなった。
“悪い”とするとちょっと語弊があるかもしれないけど、
戦後まもなくという時代設定もあって、
登場人物の全員が「何としても生き残る」執念みたいなものがあり、
全員ちょっとズルい。意地汚くも生きてやる!って、
そんな人たちばかりでしたが、映画ではそういうの薄れましたね。
特に竹野の印象は、だいぶ変わると思う。
原作では喜久雄と竹野はお互いがお互いを都合のいいように利用してたけど、
そんな感じはなくなりました。
あと、全体的に女性っぽくなった。
何がとは具体的にいえないけれど、喜久雄以外のセリフの端々とか、
なんか細かいディティールに女性っぽさを感じます。
というわけで、ラストの印象もだいぶかわります。
映画版『国宝』で思ったのは、
ついに、“たどり着いた”感ですね。
そのことを感じ取れる一文が原作にあります。
舞台に客が勝手に上がってきたシーン。
遠近が狂ったのはそのときで、舞台と客席のあいだにあるはずの何かを、
男が破って舞台に上がり込んできたのは間違いありませんでした。
≪中略≫
この歌舞伎という芸能が世に生まれたときからあった何かが、
今、目のまえで破れ堕ちたという感覚を、はっきりと感じたのでございます。出典:『国宝 (下) 花道篇』p327より
それと、喜久雄の象徴的なセリフ
「……そりゃあ、きれいな景色でさ。この世のものとは思えねえんだ。
あれを舞台でやりてえなって。
あんなかで踊れたら、俺はもう役者やめたっていいなって」出典:『国宝 (下) 花道篇』p338より
役者として、演じている部分と素の部分で一線をひいていたこと。
その堺というか“幕”がなくなったような。
とうとう境地にたどりついた喜久雄、そんな印象でした。
久々に、「原作読んで映画を見る」ことをしましたけど、
比較してみると、発見もありますね。

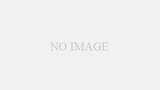
コメント