ニューハンプシャー州グラフトンの町で起こった実際の出来事。
または、現在進行形で起こり続けている出来事かもしれない。
というノンフィクション本のお話。
リバタリアンが社会実験してみた町の話
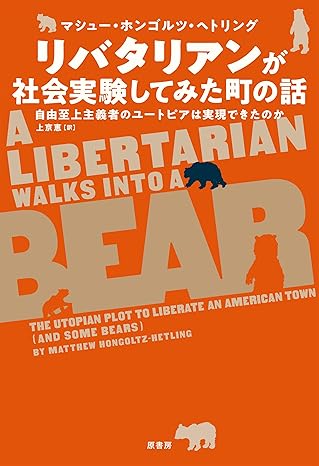 |
| リバタリアンが社会実験してみた町の話 著者:マシュー・ホンゴルツ・ヘトリング 訳:上京恵 |
リバタリアンとは何かというと、
政府の介入を最小限にする方が自由に生きられる。と
そんな考えをもつ人たちのことです。
いわゆる「小さな政府」という考え。
リバタリアンにも、考えは多種多様ありますが、
少なくとも、本書に出てくる人々はそんな考えの人たち。
自分のことは自分でする。
公共サービスに依存しすぎないことを主張する。
こう書くと、なんだかカッコいい思想に思えます。
本書でも、
「税金は低く、公共サービスは必要最低限に!」
自由至上主義者たちは個人の自由を求めます。
しかし、結果、いちばん自由になったのは熊だった!!
まるで、昔話。
原題は「A Libertarian walks into a bear」
(リバタリアン、熊に遭遇)とあるように、
いかにして、熊のはびこる街になったのか。
という過程が、ウィットに富んだ語り口でつづられ、
読み物として、超超超、面白い!
断っておくけれど、熊と共存する話ではない。
ウィットの部分を例に出すと、
町民集会は、小さなコミュニティが、権力を与えられればワシントンの政治家の失敗よりも
うまくできることを実証する機会である、また、悲惨な大失敗を演じる機会でもある。
出典:P52より
この皮肉が「小さな政府」とかかっててクセになる。
後半は作者の皮肉を求めて読んでいるふしもありましたね。
さて、リバタリアン。
読むまで、知らなかったのですが、
2001年にリバタリアンの住みやすい地域を作ろうとはじまった
フリーステートプロジェクトというのがあったそうで。
このプロジェクトで多くのリバタリアンがニューハンプシャーに移住。
中でもグラフトンはかなり厳粛なリバタリアンが集う街だったそう。
ゆる~いリバタリアンもいる中で、グラフトンは筋金入り。
とかく、公共サービスに投資をしません。
消防設備は十全でないので、火事が起きたときにだいたい手遅れ。
警察もひとり、自宅兼の警察署で手弁当で活動。
そのため、住民はほとんどが拳銃を所持し、治安もよくない。
図書館もほぼ機能不全。
公共機関のひとつに、野生生物がむやみに増えすぎないことを
監視している局もあります。
魚類鳥獣局。
野生の熊の数を管理していたここにも、グラフトンは協力を拒む。
その結果、熊にエサやりする住民(意図する、しないに関わらず)を見過ごしてしまい、
人里に食料を求めておりてくる熊を放置する結果になってしまった。
ペットの猫や、家畜、さらには住民まで熊に襲われ始める。
しかし、それでもグラフトン民は政府に助けを求めない。
大体が拳銃所持しているため、
熊に遭遇しても何とかできるという自負もあったのだと思う。
熊を慣れさせるのは危険だ
中略
人が熊に慣れるのを容認するのも、
少なくとも同じくらい危険だ出典:P188より
これは名言。
ほかにも、悪夢のピタゴラスイッチのごとく、
いろんな要素が、よくも悪くもかみ合いすぎて、
思想は自由なのに、機能は自由に住めない街として変わっていくグラフトン。
登場人物たちの最後の姿には、哀愁を感じる。
最初は大笑いしてやろうと思って手に取った本ですけど
税金を払うことの意義を図らずも考えるきっかけになりました。



コメント